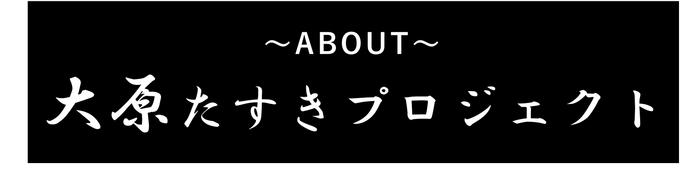-
-
- 大原はだか祭りは、古く江戸時代から行われていた。このことは大井区の瀧内神社に祭りの風景を措いた絵馬があり、その絵馬が、文久4年(1864年)に奉納されたことや別の絵馬に天保12年とあることから、160年前の天保年間にすでに、祭礼のしきたりや組織が出来あがっていたことがうかがわれる。
行事も十社まいりや浜での大漁祈願、汐ふみ、大別れ式と、華やかなものが行われてきた。江戸時代の当地域はこれといった娯楽もなく、この祭りは住民が年一回の最大の楽しみとして受け継がれてきた。古老の言を借りれば、何を質に入れても祭りの仕度を整えたといわれる。
当時は仕事の忙しさから、とかくお互いの気持ちがばらばらになりがちであった。このためこの地域の領主は唯一無二の娯楽である祭りが集団行動と意志の疎通を図ることができるという重要さを認め、神輿渡御が無事に終ったことを早飛脚で大多喜城主に報告せしめたとある。
期日も昔は8月13日から15日までであったのが改暦により、明治6年からは9月23日から25日とされ、さらに大正2年より9月23日、24日の2日に渡って行われるようになった。
この祭りは他に比類ない勇壮な祭りであることから、戦時中、当時の氏子総代が警察に祭り騒ぎでもないとして自粛を申し入れるに、地域住民の士気を鼓舞するによいことだから大いに活発な祭りを行うよう署より申し渡されたと伝えられる。(いすみ市役所引用) -
-
-
-
氏子たちの想い
- 各都道府県の市町村のどこをとっても同じ悩みをもっていると思うがこのいすみ市も同様で地元で生計をたてたくとも働き口が少なく、都会へ出ていく若者も少なくない。そこで結婚し、子供が生まれ田舎に帰ることをためらいその地にとどまる選択をする者も多い。
しかし年に一度、必ず帰る時期がある。それがこの大原はだか祭りである。まるで町の同窓会のようにこぞって集まる唯一の行事である。この時期になると普段静かなJR大原駅は笑顔でにぎわう。久しぶりに会う顔はどこか凛々しくどこか寂しい顔をしている。ある氏子は祭りの恰好をすると先祖を感じるという。
そう感じるのには大きな理由がある。
それはいにしえより変わらぬ恰好で変わらぬ想いを継承しているからなのである。神輿に手を添えた時、先人たちより渡されたバトンを受け取ったように感じるのだ。先人の命は亡くなっても魂はこの祭りに宿り、その魂を感じることで先祖の存在を感じるのだ。それは血がつながっていなくとも、この大原の地で生きた全ての人のへの敬意の表れでもある。過疎化が進み、街並みが静かになっていってもこの祭りのバトンは落とすことなくぎゅっと握りしめ、地元大原の五穀豊穣・大漁祈願・生きとし生けるものの幸せを願うのだ。そして2日間存分に地元を堪能した氏子たちは生き生きとした誇らしい顔つきでそれぞれの戦場へと戻っていくのである。
傷を癒し心の充電をし、また来年のここで会う約束をして・・・ -
-
-
-
祭り唄に込めた想い
- この祭りの三大みどころの一つで、怒濤の中で神輿が数社もみあうさまは勇壮豪快の一語につきると言われる「汐ふみ」は圧巻でどこの祭りにもない様は毎年何万人もの観客が場所取りをしてまでカメラに収めたくなる壮大なものである。しかしもう一つ欠かせないものは氏子が神輿を担いでねり歩く際に唄う祭り唄だ。
- この祭り唄は大原に生まれ育った子供はものを話す前に覚えるなじみの唄でその歌詞にはこの祭りへの想いが全て凝縮されている。
作られる祭り唄の歌詞を現代の言葉で要約すると
「この大原というところはすごくいいところだ。人も町も自然の恵みも潤いに満ちている。そんなやつらで今年も盛り上げていくぜ!大原はだか祭り。どんなところに住んでいてもどんな職についていても全く関係ない。この祭りを盛り上げるやつはみんな仲間だ。お前たちの幸せを願うぜ!今年も盛り上がろう!祭りは楽しいなぁ。今年もお前に会えたよ!楽しすぎて今日が終わらなきゃいいのになぁ。お前たちともバイバイしたくないぜ。だからまた来年も盛り上がろうぜ!またここで会おう!」
そのようなことを唄っている。
この祭り唄もまたいにしえより受け継いでいる守り唄なのだ。
氏子集の心の声を唄にして神々を担ぎ各々地域を練り歩くのだ。 -
-
-
切実な現状
-
- 100年以上も続く歴史ある祭りにも大きな問題がある。
それは財政難である。
この祭りは氏子たちの有志資金で賄っているのだ。大原と大きく括っているがそのお社の数は現在18社ありそれぞれに氏子集がいてその数同様、神輿もある。お社は何百年もその地で氏子集を守り、この祭りも成り立っている。しかしながら毎年修繕が必要で有志の額にも限界がある。日本家屋の修繕、また神輿の修繕はとても難しく、一つ直すにも莫大な費用がかかるのだ。日々の生活を抱える氏子集も重なる修繕費に奔走するが追い付いていけない厳しい現状を目の当たりにしながらもこの祭りを途絶えさせることのないように最善を尽くしながらこの大原はだか祭りを守っているのだ。 -
-
地元企業として~プロジェクト実施の理由~
-
- 過疎化が続くなかでもこの大原の地で商いをしている企業はいくつもあります。
五穀豊穣・大漁祈願の名の元に大原港で漁業を営むもの、農家、飲食店、造り酒屋、宿泊施設など様々な企業が地元いすみ市の復興に尽力をしています。それはこの大原はだか祭りの由来にも通じており、氏子たちが帰る場所、変わらず祭りができる場所、笑顔を絶やさない場所を変わらず守っています。去るものもいる中、ここに残り、いすみ市に対して自分たちに何ができるのか?大原はだか祭りを守るために、氏子たちの士気を守るために、先人たちが守り抜いたこの思いを未来へ繋げるために何をすればいいのか?
そこで辿り着いたのがこのチャリティー目的のクラウドファンディングです。
自分たちの商いを通してこの大原はだか祭りのチャリティーに名乗りを上げるスターターとして、大原はだか祭りで各神社への奉納酒を託されている木戸泉酒造と、地元で捕れた海産物を加工・販売しているアルファの2社が手を組み、立ち上がることにいたしました。
日々の商いをさせていただいている感謝と地元大原に対する敬意を表し、沢山の方にいすみの魅力と大原はだか祭りのこの幻想的で熱き思いをご賛同いただきたく特別なセットをご用意し、ご賛同くださった皆様と共にいにしえより守り抜いている大原はだか祭りを盛り上げていきたいと考えています。
このクラウドファンディングにていただいた支援金は、掲載手数料やリワードの準備費用等の必要経費を除くすべてを、大原はだか祭りを支える全18社の神社へ按分し奉納させていただきます。 -
プロジェクト実行者の想い
- 木戸泉酒造は100年以上も前よりこの大原はだか祭りの御神酒を造らさせていただいております。
それは毎年変わらず何も変わらずに毎年のこととして当たり前の様に造ることでした。しかし2024年のお祭りの際に何気なく話している氏子の話が胸に残りました。
「今年はお宮の〇〇の修繕があるんだってさ。来年は神輿の〇〇の修繕の予定で・・・金がかかるんだよなー。寄付したくても限界があるし。でもやるっきゃないんだけどなぁ・・・まぁどこのお宮も同じだからなぁうちだけじゃないんだよなぁ」
そんな氏子さん達は材料高騰で御神酒の値上げに対して何も異論なく合意してくれ、今年も祭り酒を購入してくれています。大原の街の人にとってこの大原はだか祭りとは生きる目標であり、明日の活力でもあります。みんなが笑顔になるはずの場所が財政難によって消え薄れていくという事態があってならないと思いました。
明治12年より造り酒屋を生業とし、大原の地で御神酒を作り、造り酒屋以前は漁業・農業と商いをし、続く歴史は江戸時代まで遡ります。このはだか祭りとともにこの地にたたせていただいているものとして何ができるのか?そう切実に考えました。私たちは日々同業以外にも大原の街中の企業様とタッグを組み沢山の企画を世に出してきました。
今回のたすきプロジェクトはまさにその象徴ともいえます。
アルファ様に相談した時も「利益は要らない!祭りん為にうちを利用しな!」と粋なお心をいただきました。みんな想いは一緒です。無くしてならない心と共に伝承していく、仲間と共に手をとりあい、未来へたすきを繋ぐ。そして今回を第一弾としてこれからもいすみ市大原の企業様とタスキをつないで参ります。
電子化がすすみ、隣近所との付き合いを簡素化することが当たり前の世の中で相手を思うこの心意気をこれからもこの町は大原はだか祭りをとおして伝承していきたいと思っております。
「祭りを盛り上げるやつらはみんな仲間だ!仲間が困ってたら手をかすんが大原ん奴だ!」
この精神は100年以上受け継ぎそしてまたさらに100年繋げていきたい精神です。ぜひ、この勇壮豪快!大原はだか祭りを体感しにいらしてください。そして皆様のお力をお貸しください。
守ることの大切さと守りぬいていく先にある笑顔を皆様と共に分かち合いたいと思っております。 -
- 大原たすきプロジェクト2026、大原たすきプロジェクト2027...と、こちらの画像により多くの事業者さまの名前が載る(プロジェクトに賛同していただける)ような象徴的なチャリティープロジェクトになるように、単発のプロジェクトではなく、継続的に活動したいと決意しています。
-
リワード一覧
-
¥3,000 御礼のメッセージ
-
¥5,000 アルファの干物(国産あじ)
-
-
¥10,000 木戸泉酒造の御神酒
-
-
¥15,000 鈴染の萬祝染トートバッグ
-
-
¥15,000 アルファと木戸泉のたすきセット
-
-
¥25,000 鈴染と木戸泉のたすきセット
-
-
御神酒のデザイン
-
大漁を祝う萬祝半纏をラベルに
-
-
- リワードとして皆様にお届けする御神酒のラベルには、大漁祝いの祝儀として使われた「萬祝半纏」のデザインを施しました。
デザインにご協力いただいたのは鴨川の鈴染様
ご協力いただきまして、ありがとうございました。
皆様にはぜひ、このラベルを眺めつつ、
豊漁を願う「大原はだか祭り」に思いを馳せていただければと思います。 -
参画企業紹介①木戸泉酒造
-
- この地で造り酒屋を始めた明治12年(1879年)。屋号である「木戸」に酒をあわらす「泉」で「木戸泉」を銘柄としてきました。
昭和31年(1956年)、私の祖父(三代目蔵元)の強い想い「旨き良き酒」をもとに独自開発した高温山廃仕込み。以来、60年以上の永きに亘り頑なに取組み続けてきた自然醸造。この自然醸造による旨き良き酒をモットーに、味わい深くキレのある、酔い覚め爽快な食中酒をこれからも皆様にお届けしてまいります。
酒造りに水は命ともいえるもの。その大地の恵を頂き、蔵人が魂を込めて酒を醸す。
米もまた大地からの恵。毎年収穫される原料米に感謝を忘れず、毎年無事に酒造りができる喜びをスタッフみんなと共有していきます。
酒造りは毎年毎年が挑戦の連続です。
高温山廃仕込みのさらなる可能性・進化を追い求めて、今後も人・水・米と向き合って行きます。 -
-
代表者メッセージ
-
- 私が継承した酒蔵では私が生まれる前からこの「はだか祭り」で御神酒として使用してもらっております。それは子供の頃より当たり前ことだとそのことを気にもとめていませんでした。しかし2020年コロナウィルスの蔓延によって毎年当たり前に開催されていた祭りが中止となり、目の前の世界が変わりました。
売上は当然のことですが、それよりも大原のまちに「祭りがない」という事実がとても衝撃的でした。今では開催も元に戻り、また当たり前は取り戻されましたが、私の中であれから何年もずっとどこか引っかかる何かが胸の中にあり、何とも言えない気持ちでいたのです。
この地に酒蔵がある。そして100年以上も続く祭りがある。この祭りを毎年楽しみにしている氏子がいる。この環境は変わらないのに、社会情勢は変化していく。『何か自分にできることはないか?』そう思うようになりました。
その考えを後押しするように頭に思い浮かんだのが幼いころから参加している『大原はだか祭り』で大人の人達がいつも声を掛け合い『みんなができることをやる・一人は誰かのために』という見えない約束事でした。
祭り唄と共に頭によぎってくるのはそんな大人たちの粋な計らいの光景だったのです。
今自分が大人の立場になって、次世代に残したいものは何かと問われたら、やはりこの心意気だと思います。
今回の『たすきプロジェクト』はまさにそのことを改めてきづかせてもらいそして形にできるチャンスだと思いました。笑顔溢れる祭りがより続くようにそしてこの粋な心意気がずっと続くようにぜひご賛同いただければと思います。 -
参画企業紹介②海の直売所 アルファ
-
- 千葉県いすみ市の港の朝市で知られる、大原漁港と大原海水浴場のほど近く。木のぬくもりを感じるログハウス風のお店を見つけたら、そこが『海の直売所アルファ』です。
千葉県いすみ市大原漁港のすぐ近くで、干物職人たちが丹精込めてつくり上げる干物を工場直売でお買い求めいただけます。干物職人こだわりの干物や、お土産に最適な海産物のほか、海をテーマにした雑貨なども販売しております。
一番のおすすめは、出来上がりから一度も冷凍をかけていない『出来立てひもの』
漁師の家庭で育った店主が魚を厳選。シンプルな素材にこだわり、身は柔らかくふっくらと、脂ののりもほどよく仕上がっております。
スタッフ一同、笑顔で皆様のご来店をお待ちしております。 -
-
代表者メッセージ
-
- 千葉銀行さんから『たすきプロジェクト』のお誘いをいただいた時正直参加したい気持ちと忙しい時間の中でできるのか?中途半端になるならそもそも不参加にした方がいいのか悩んでおりました。そんな時、木戸泉さんからこの『寄付目的のたすきプロジェクト』の話を聞いて、ましてや地元の祭りに貢献したいという想いをきいてこれは『やりたい!』とすぐに思いました。私はこのはだか祭りには特別な思いがあり、日々自分なりには祭りに貢献してきたのですがこのたすきプロジェクトが成功したら理想的な町づくりの橋渡しになるのではないかと希望すら思い描かれました。
祭りは代々下へ下へと繋げていきます。儀式・習わし・ルール伝えても伝言ゲームのように変化してしまうことがあり、それもまた良しと腹落ちさせることもあります。
でもそれが地元企業としての立場と想いを乗せられて、なおかつ参加企業が増えてこの思いを繋げていけたらこんなに嬉しいことはないと思ったのです。
『若ぇもんが考えたこと・好きんやりなよ!困ったら言えよ!助けてやっから。』このフレーズは私も子供の頃、町の大人に教えてもらいました。今まさにその思いを自分の事業とともに町へ貢献できるということはとても素晴らしいと思います。ぜひこのフレーズが年に一度の祭りの時以外も日々の商売の中でも共存共栄が広がりそしてこれこそが当たり前になることを願っております。 -
参画企業紹介③鴨川萬祝染 鈴染
-
- 江戸時代から続き、千葉県房総半島が発祥と考えられている「萬祝(まいわい)」。
長着の裾には鶴亀・松竹梅・宝船など縁起の良い図柄や大漁に獲れた魚などが大胆かつ色鮮やかに描かれています。そもそも「萬祝」とは大漁祝いのことを指しましたが、いつしか大漁祝いの晴れ着を「まいわい」と呼ぶようになりました。
昭和になるとライフスタイルの変化もあり、大漁祝いに萬祝を配る習慣がなくなってしまいました。しかし、萬祝染の技術は今も色褪せることなく初代から受け継がれており、現在は祭半纏やお祝の額装品など、様々な作品に技術が活かされています。また、千葉県から生まれた漁民芸術文化を残すため、ワークショップなどを通し文化の伝承にも積極的に取り組んでいます。
今年、鈴染は創業100周年を迎えます。創業当時から受け継がれる技術・歴史を大切に紡ぎながら、今後も少しでも多くの方に喜んで頂けるような作品作りに努めてまいります。 -
代表者メッセージ
-
- 昔は当たり前のようにあった文化がいつの間にか無くなってしまう。そんな光景を仕事柄たくさん見てきました。時代に合ったものが残っていくことは当たり前のことかもしれません。
しかし、文化には人・地域が紡いできた歴史や大切な想いが刻まれています。特にお祭りはその地域を象徴する文化でもあります。
大原はだか祭りにも、家族・友人との大切な思い出、時にはぶつかり合いながらも紡いできた地域の繋がりなど様々な歴史が刻まれていると思います。私どもも萬祝という文化を残していく担い手として、大原はだか祭りという素晴らしい文化を次世代の子どもたちに伝え、残していくお手伝いが出来ないかという想いで今回のプロジェクトに協力いたしました。
今、当たり前にある素敵な文化は何もしなければ衰退してしまいます。
みんなで協力し、この素敵な文化を次世代へ紡いでいければと心より願っております。 -
その他、ご協力いただいた皆様
- 大原はだか祭り写真提供 井上久雄さま